
新築するよりもリーズナブルに理想の住まいを手に入れられることから、人気のリフォーム・リノベーションですが、工事費のほかにもさまざまな諸費用がかかります。特に見逃しがちなのが税金です。中古住宅の購入時だけでなくリフォーム・リノベーションにあたっても、各種税金がかかる可能性があります。
今回は、そんなリフォーム・リノベーションにまつわる税金のあれこれを徹底解説。固定資産税に関する疑問にも答えていきます。
事例集ダウンロードはこちら
リフォーム・リノベーションでかかる税金の種類

最初に、リフォーム・リノベーションによってかかる主な税金の種類を見ていきましょう。これから紹介する税金は必ずかかるとは限らないため、納めなければならないケースも合わせて紹介していきます。
印紙税
リフォーム・リノベーションを実施する際には、施工会社と工事請負契約書を締結します。このような取引では契約書に税金が課されます。これが、印紙税です。印紙税の税額は契約金額によって増減するよう定められており、具体的には次のとおりとなっています。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
建設工事に関する請負契約書については、2024年3月31日まで上記のとおり軽減税率が定められています。
参考:建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
登録免許税
一体型ローンなど抵当権を設定して金融機関から融資を受ける場合、抵当権設定登記にかかる登録免許税を納めなければなりません。本則税率は融資を受けている金額の0.4%と定められていますが、2024年3月31日までに中古住宅を取得して自身で住む場合には0.1%の軽減税率が適用されます。
たとえば、中古住宅購入+リノベーションで3,000万円の一体型ローンを組むケースであれば、登録免許税は通常3,000万円×0.4%=12万円を納める必要がありますが、軽減税率適用期間中は1/4の3万円になります。
参考:No.7191 登録免許税の税額表
不動産取得税
不動産取得税は、本来物件の取得時に1回だけ納めなければならない税金ですが、リフォーム・リノベーションによって増改築を行うケースでは、新たに不動産取得税が課せられる場合があります。不動産取得税の税額は不動産評価額×4%ですが、2024年3月31日までに取得した土地・建物については3%の軽減税率が適用されます。
なお、増改築後の床面積が50m2以上240m2以下の住宅においては、一定の控除があるため、実質240m2を超える増築分がある場合のみ適用されると考えてよいでしょう。
参考:不動産取得税
固定資産税
リフォーム・リノベーションに伴う増改築などで資産価値が向上した場合、固定資産税が増額される可能性があります。どのような場合に固定資産税が増減するのか、この後詳しく解説していきます。
リフォーム・リノベーションで固定資産税はどうなる?

リフォーム・リノベーションによって固定資産税が増額されるケースがあると紹介しましたが、反対に一定期間固定資産税が減額される場合もあります。具体的にどのようなケースで固定資産税額に影響が出るのか見ていきましょう。
固定資産税が上がるリフォーム・リノベーション
家の中の一部をリフォームしたくらいでは、固定資産税には影響しません。リフォーム・リノベーションによって固定資産税が上がる可能性があるのは、「建築確認申請」を要する場合であり、具体的には次の3つが挙げられます。
- 増築によって床面積が増えるリフォーム・リノベーション
- 主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根または階段)を一定以上修繕、模様替えするリフォーム・リノベーション
- 建物用途を住居から店舗や事務所などへ変更するリフォーム・リノベーション
これらのリフォーム・リノベーションは、建築確認申請が必要となり、改修によって建物の価値が上がったとみなされる可能性があります。結果として固定資産税評価額がアップし、工事した翌年以降の固定資産税が上がるのです。
なお、2点目については、建築基準法で定められた「4号建築物」以外の住宅のみ建築確認申請が必須となります。建築確認申請が必要なリフォーム・リノベーションの種類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
参考記事:リノベーションは検査済証が必要?確認申請が必要な工事の種類や、検査済証がない場合の対処法を解説
一定期間固定資産税が下がるリフォーム・リノベーション
リフォーム・リノベーションの内容によっては、固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。以下のいずれかに該当するようであれば、工事が完了した年の翌年1年分の固定資産税(家屋分)が1/3〜2/3軽減される可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
- 耐震リフォーム(固定資産税を1/2減額)
- バリアフリーリフォーム(固定資産税を1/3減額)
- 省エネリフォーム(固定資産税を1/3減額)
- 長期優良住宅化リフォーム(固定資産税を2/3減額)
リフォーム・リノベーションで活用できる減税制度
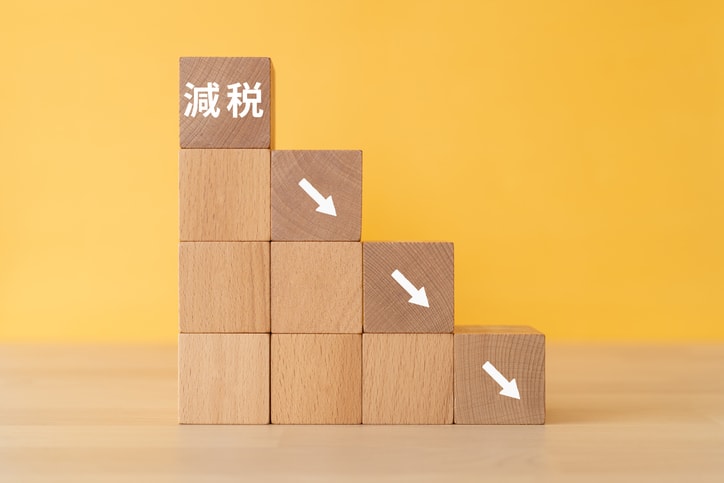
前項で紹介した固定資産税の減額措置のほかにも、リフォーム・リノベーションで活用できる減税制度があります。中古住宅を取得してリフォーム・リノベーションするケースで減税される可能性があるのは、所得税・贈与税・不動産取得税の3つです。
所得税の減税(控除)制度
一定の基準を満たすリフォーム・リノベーションを行い、確定申告において必要な手続きを行うと次の2つの減税制度より、いずれかの適用を受けられます。
- リフォーム促進税制
リフォームローンの利用有無に限らず適用可能。耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化のいずれかに該当するリフォームについて、工事が完了した1年間の所得税が最大105万円控除されます。 - 住宅ローン控除(減税)
返済期間10年以上のローンを借り入れる場合に適用可能。詳細はこちらの記事で解説しています。
参考記事:2022年版住宅ローン減税について解説!押さえておきたいポイントまとめ
贈与税の非課税措置
不動産や金銭などの贈与を受けたら、受け取った資産額に応じて贈与税を納めなくてはなりません。リフォーム・リノベーションを行うための金銭を直系尊属(親や祖父母など)から受け取った場合には、一定金額までの贈与について贈与税が非課税になるという措置が2023年12月31日まで適用されます。
非課税枠は、省エネ性・耐震性・バリアフリー性のいずれかが高い住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円。自らが所有・居住する住宅で改修後の床面積が50m2以上240m2以下であることなど、一定の条件を満たす住宅が対象です。
不動産取得税の軽減措置
個人が新耐震基準に適合しない中古住宅を取得して、取得後6ヶ月以内に耐震改修工事を実施、耐震基準適合診断書等を取得したうえで居住している場合、築年数に応じた不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
原則住宅の不動産取得税から控除を受けられる制度ですが、一定の要件を満たすと住宅用の土地についても不動産取得税の控除を受けられる可能性があります。
まとめ
住宅取得時だけでなく、リフォーム・リノベーションにおいても税金を納める必要があります。印紙税のようにほぼ全員が納めることになるものもあれば、登録免許税や不動産取得税のようにケースごとに扱いが異なるものもあるので要注意。また、固定資産税についてはリフォーム内容に応じて増減する可能性があります。
今回紹介した内容を参考に、自身が計画するリフォーム・リノベーションで納めなくてはならない税金について、事前に調べておくのがおすすめです。
事例集ダウンロードはこちら

